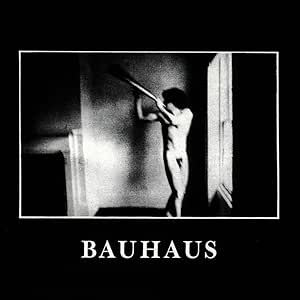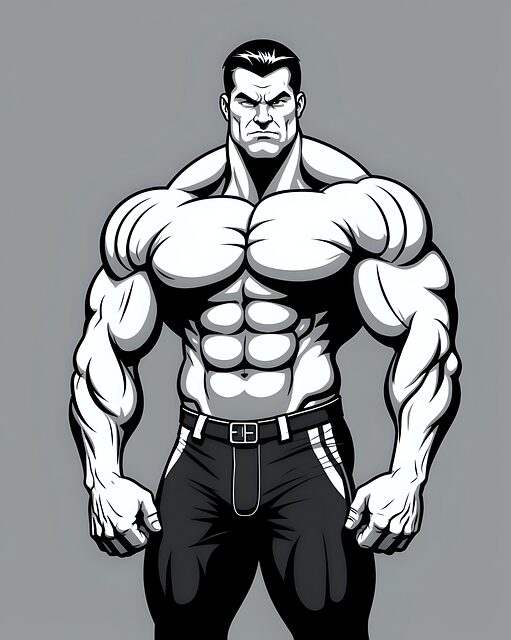ライブが行われた場所は、たしか渋谷公会堂でした。渋谷という街も、今ほど垢ぬけていなくて、いろんなところに、中古レコード屋や楽器屋が点在しており、そういうところに、学校帰り、行き場がよくわからない私みたいな人が徘徊していたり…。
たしか、学校からそのまま、ライブ会場に行ったような記憶があるんですね。学生服着て行ったように思えます。

会場に着いて、いちばん驚いたのが、客層でした。
当たり前にバウハウスのファンが来るわけでしょうけれど、お客さん、ずらっと黒ずくめなんです。ほとんどが女性でしたが、今でいう、ゴシックパンク、という装いでしょう。
しかし、あの当時、髪を逆立てたり、モヒカンにしたり、あるいは、歌舞伎の隈取さながらのアイラインを、ブラックで太く入れたり、などというのは、相当に勇気と覚悟がなくてはできない時分でしたが、そういう人が、かなりの数、いたのですね。

で、彼らはとにかく、喋りません。だから、不穏な雰囲気が高まる一方…
私は二階席で、周囲はみんな、一人で訪れている、ゴシックの女性陣。私をふくめて、ずらっと、鬱的ムードを放っているのだから、演奏者たちは、因果応報とはいえ、キツイものがあったでしょうなあ…!
ステージ中央に、マーシャルのキャビネットが三台積みされていて、ギタリストが出て来るや、暗鬱なコードをかき鳴らします。

たしか、会場、ちょっとざわついたくらいで、基本、静かなんですね。
ただ、まだ感性が鈍く、そのうえ病気で鈍麻していた私にも、会場全体に熱気が充満して、汗ばんでいくのがわかりました。こうした緊張感のある盛り上がり方は、格闘技の会場に似ていて、あまり音楽のライブでは体験できないものだったように記憶しています。
会場が静かな興奮に包まれ、お客の声も聞こえるようになったのは、やはり、ヴォーカリストでバンドの「顔」であるピーター・マーフィーが登場してからでした。
がりがりに痩せた体躯の、彫りの深い美男子で、それが低い声で地響きのするような歌唱をするという、やはりモテ要素はミスマッチから、という見本といえる人物…

バウハウスって、基本、slowでheavyで、気だるい楽曲が主体なのですが、轟音でそれらを連発して、会場に「うねり」みたいな空気が出てきたあたりで、まだレコードでは出ていなかった「テレグラム・サム」などの、アップテンポの激しい、しかも痙攣的なナンバーが入ってくるから、会場は異様な盛り上がりを見せました。
観客は総立ち。私の周囲のゴシックガールたちは、体を少し弾ませながら、微妙に回旋させるという、不思議なムーブで踊っていた…というか、操られていたとしか……
ライブが最高潮に達したのは、細身のピーター・マーフィーが、そのまま「骸骨」、スケルトンに扮したときです。

緑の蛍光塗料で骸骨が描かれている、真っ黒なタイツで全身を包む、という、真似をしたら、ほとんどの男が即・変質者の烙印を捺されてしまういで立ち。
曲は「ベラ・ルゴシの死」だったかなあ…それを歌いながら、客席に踊り込んだ彼は、踊り狂いながら、お客の間を歩き回り…
そんなこんなで、忘れられない光景とサウンドに満ちたライブでした。
あのときのゴシックの人たち、どうしているのだろう…