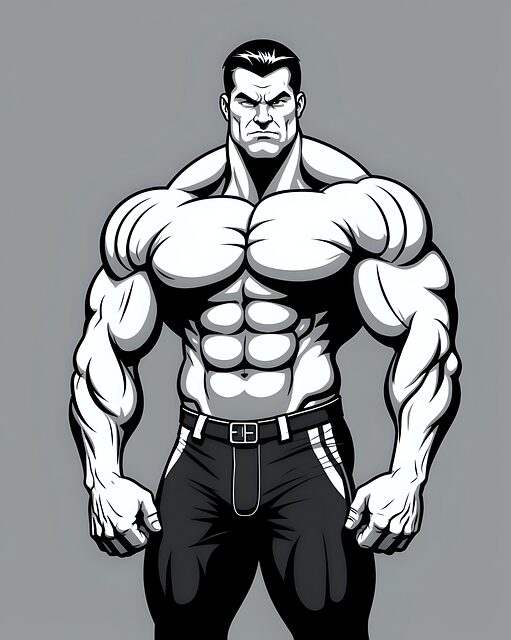お久しぶりです<m(__)m>
今回から、画像が添付できるようになりました。簡単なことでしたが、苦心しました。
今回、お付き合いいただいた方々には、洋楽のドラッグ関連の歌、というか、曲の話題を…。
私は、若年期に「うつ」を患ったため、必然的に引きこもったりすることになり、友人知人などを失ってしまいましたので、体を動かす元気など皆無だったから、ギターなどにはまっておりました。
今思うと、それで左右の指を個別に動かす訓練をしたのが、いろんな意味で良かったのではないかな、などとも思えるのですが、そんな話は、またいずれ。
で、はじめのうちはクラシック音楽を聴いていたものの、当たり前のように、軽音楽に傾倒するようになり、なかでも、洋楽ロックに突っ込んでいく流れになったのでした。

なにしろ、昭和の当時は、今のように、かなり正確な歌詞が、すぐに検索で見つかったり、かなり適切な翻訳がすぐに手に入る時代ではありません。
ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、デヴィッド・ボウイの「ジギー・スターダスト」(架空の人物名です。ボウイ自身がステージで、このキャラに扮しました)が「屈曲する星くず」という邦題で発売されたり、エアロスミスの「ウオーク・ジス・ウェイ」(だったかな?)が「お説教」という邦題だったり、ザ・フーのアルバムに「俺は百姓」という曲があったりで、なかなか、いい加減な仕事がまかり通っていたように思えます。
こちらもまだガキといえばガキでしたから、まともな英語など、じつのところ、あまり理解できていませんので、洋楽が好きでも、曲を覚えるのが大変でした(別に歌詞覚えなくてもいいかもしれないんですが、意味不明でも、覚えたくなるもんですねえ・・・!)。
…いったい、なんの話をしたかったのか、よくわからんようになりました(呆然)。
なので、タイトルに回帰します。
70年代の洋楽ロックの世界に、たぶん一ジャンルといえると思うのですが、ドラッグソング群がありました。

今となると、そういうのは歌ってもいけないし、そのような曲はなかったこと、とかになっているらしき雰囲気なので、忘れ去られていくのかも、しれません。
…昔、保守的なエド・サリヴァン・ショーだかに出演したドアーズのジム・モリソンが、大ヒット中の「ハートに火をつけて」を歌う、事前に局側から、歌詞のなかにある「higher」の部分を、ほかの言葉に差し替えろ、と言われたのに、そうしなかったから、出禁だかになった、という逸話がありますが(ハイ、は、ドラッグで気分が「飛ぶ」、いい気持になった、みたいな意味合いのようです)、今は、世界的に、エド・サリヴァン・ショーみたいになったらしく…
本当に、70年代の曲の歌詞のなかに出てくる薬系の「high」の部分が、リメイクのときに、別の「人にやさしい」言葉に差し替えられていたりしています。
エリック・クラプトンの「コカイン」とか、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「ヘロイン」などという曲は、どう扱われているのだろう…前者などでのクラプトンのギターは、素晴らしいのですが、アルバムから削除されたりして…。
たしか、少し前でしたら、イギー・ポップが明らかに、何かとんでもないものを摂取したらしき、獣のような目で、客を煽りまくるライブ映像や、ほとんどゾンビ状態でステージに佇立しているジョニー・サンダースの姿などが、YouTubeで視聴できましたが、今は、そういう映像もなくなっているようです。
ニール・ヤングが、有名なコンサートで、両方の鼻の穴にコカインの塊を突っ込んだまま、ハイテンションでギターを弾くという、物凄いシーンもあったのですが、噂では、その映像はCG加工されて、コカインだけが消去されたそうです。
さすがに、ニール・ヤングを映像から消去する措置は取らなかったみたいですね。
次は、ステロイドですね…!